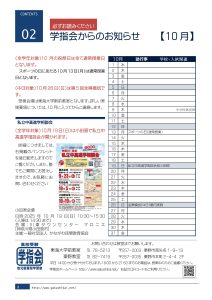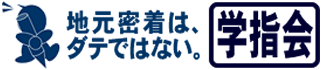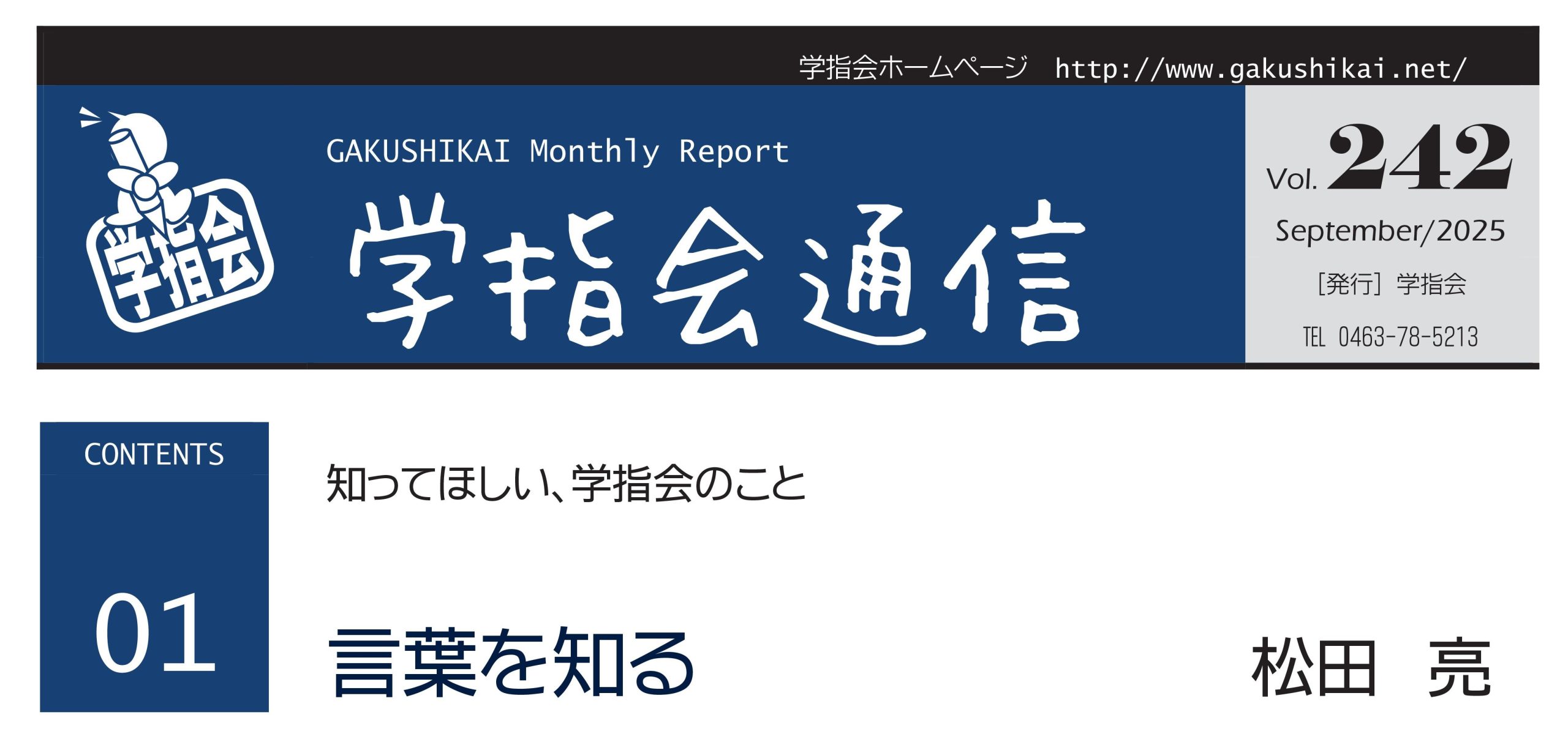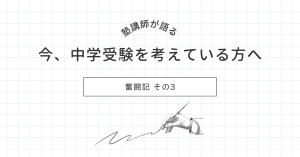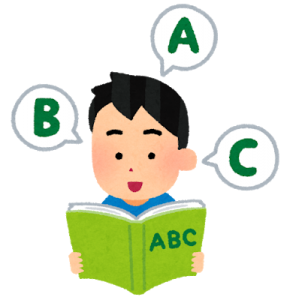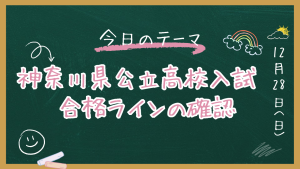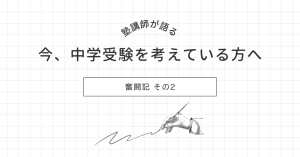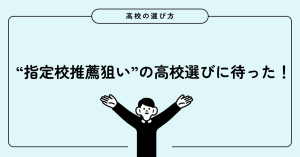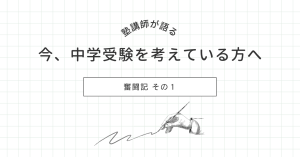学指会通信(2025年9月発行)より
「暑さ寒さも彼岸まで」とよく言われるように、夜は肌寒くなってきました。今夏の暑さは格別で、昼出勤の私は日傘とタオルが手放せず、やせる思いで出勤していました。しかし、この夏の体重は過去最高を更新しました。本当に不思議です。
さて、先日のお彼岸に親族一同でお墓参りに行ってきました。その後の大いに盛り上がった食事会の席で「がんめいころう」という言葉が出てきました。最初に耳にしたときは日本語かどうかも判断できなかったのですが、すかさずGoogleで調べたところ、「頑迷固陋(見識が狭いため古い習慣に固執して正しい判断ができないこと)」という四字熟語でした。
発話者にとっては何気ない日常的な言葉でも、受け手には耳慣れない(全く知らない)言葉というのはたくさんあります。例えば「とらぬ狸の」ときたら「皮算用」が当たり前なのですが、「皮算用」という言葉自体の意味から高校生たちの認知度が低かったため、先日びっくりしました。コミュニケーションは共通認識の上で成り立つものであり、学齢とともに獲得言語を増加させないと成熟されたコミュニケーションにはなりません。
また、大学進学や就職において「言語化」する力が注目されています。探求学習や協働学習(グループワーク)では他者理解と言語化能力が活動の肝となります。感情を言葉にして相手に伝えることは私も苦手ですが、中高生には喫緊課題のスキルのように思えます。それを世間では「コミュニケーションスキル」と呼ぶのでしょう。語彙のインプットなしに言語化といったアウトプットは無理です。
英語学習に注目が集まりがちですが、母国語という土台がしっかりとしていないと上手く積み上げられないと思います。学指会は漢字能力検定の準会場にもなっています。もう少し漢検重視の指導プログラムを構築すべきではないかと考えています。言葉を知ることは様々な学びに波及していくものです。確かに読書も語彙を増やす良い方法ですが、家庭や様々な世代の人々との会話でも、新鮮な言葉に触れることができると思います。秋の夜長に電子機器を介さずリアルなおしゃべりをする時間を持ちませんか。