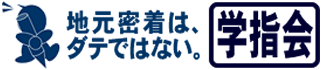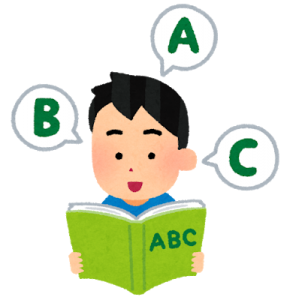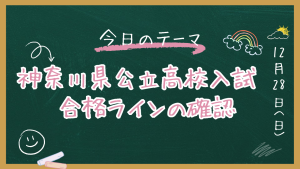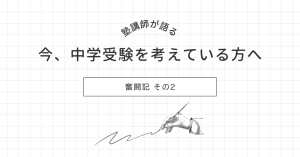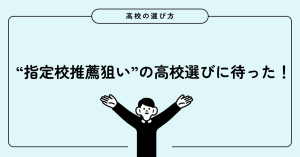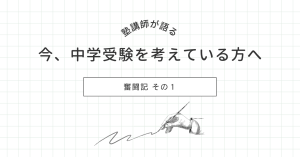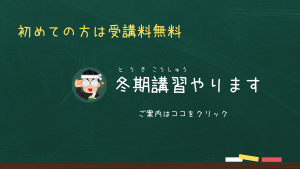こんにちはマツダです。今回のブログも長男の高校受験に係わる出来事の続きです。
我が子が生徒
前回までに書き忘れていましたが、子どもたちは二人とも塾では私が英語と理科を指導していました。周りの生徒たちも事情を知っていましたので、公平性を保って授業することが最初は大変でした。しかし、現在の子どもとの関係性から考えると良かったなと思ってます。
「親の立場」と「塾の先生」の立場を同時に経験している人は珍しいのではないでしょうか。その当時は深く考えていませんでしたが、今考えるとレアなケースだと思います。保護者の方には参考になることがあればよいと思い書いていきます。
親としての立場
子どもたちも、塾の宿題や小テストができない訳にはいかないので、大変だったかもしれません。塾で指導をしているので、家では勉強についてほとんど何も言いませんでした。また子どもたちからも勉強についての質問を家ではしませんでした。妻はもともと勉強には無頓着なので、家庭が「セーフティーな場所」である状況は保たれていたと思います。
距離感の取り方では、最初の子どもである長女が『実験台』のような扱いになってしまい、申し訳ないなと思うこともありました。
目的を持った勉強になるように
自らの意思で勉強ができるような声掛けはしていました。勉強の習慣化です。私自身の反省から、勉強する「時間」よりも、勉強する「目的」を優先するように促していました。受験期までは基本的には毎日机には向かい、与えられた課題を確実にこなすことのみをしてました。
二人とも部活もしていたので、厳しいことは言いませんでした。ただし携帯電話(スマホ)の取り扱いのルールは、厳しく守らせました。
ルールを作り、そしてそれを守らせることが、非常に大切だと思います。受験以前に『スイッチ』作りをしておくのです、オンとオフを切り替えるものなら、何でも良いと思います。ただし前提として子どもの手本となる親の行動は必要です。
勉強モードになるきっかけ
長女と長男の違いはこの『スイッチ』の違いです。長女は「ルールだから守る」と考え、長男は「必要だから守る」と考えていました。勉強モードになったのは「必要なこと」が「志望校に合格したい」という気持ちになったことだけだと思います。
私自身は、中1から母によって、毎日2時間以上勉強する習慣を身に付けられていました。長女と似ている思考で続けていました、そのため「勉強すること」自体が目標になってしまっていたのです。この反省から「何の目的に勉強するのか」をはっきりさせることが必要だと思っているのです。
また以前の記事にも書きましたが、長男の場合は、内申点の評価が想像以上低くかったことへの悔しさもスパイスになったと思います。
スイッチの入れ方
スイッチは入れようと思っても入りません、兆候が出たときに一気にその炎を煽るしかありません。幸いにも私はプロなので、効果的なアドバイスができたと思います。必要な問題集や勉強法も伝えることができました。
しかしそれができたのは、『理解してもらえている』という信頼関係があったからです。いくら受験のプロであっても信頼関係がなければ、効果的なアドバイスにはなりません。幼いころから一緒によく出かけていたことが良かったと思います。

生命の星・地球博物館

東京国立博物館

MOA美術館
ルールを守らせる、信頼関係を築く、タイミングを見計らう、この3点がポイントだと思います。
※ここで言う「信頼関係」は最低限の受験に関する知識を持つことを指します。子どもに「こんなことも知らないの?」と言わせないようにすることです。
まとめ
これらが我が家の子育てで感じた、主に長男の高校受験の際の出来事です。この仕事をしてよかったことの一つは、積極的に子育てに参加できることです。赤ちゃんの時から『夜の担当』として面倒をみていました、また仕事は午後からなので午前中に一緒に公園やプールに行ったりしていました。経済的には裕福ではありませんでしたが、今思い返すと楽しい思い出です。
このような経験をしていますので、勉強のことはもちろん、勉強以外のことでも不安なことや心配なことがありましたら、お気軽に相談ください。LINEでも大丈夫です。